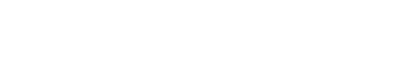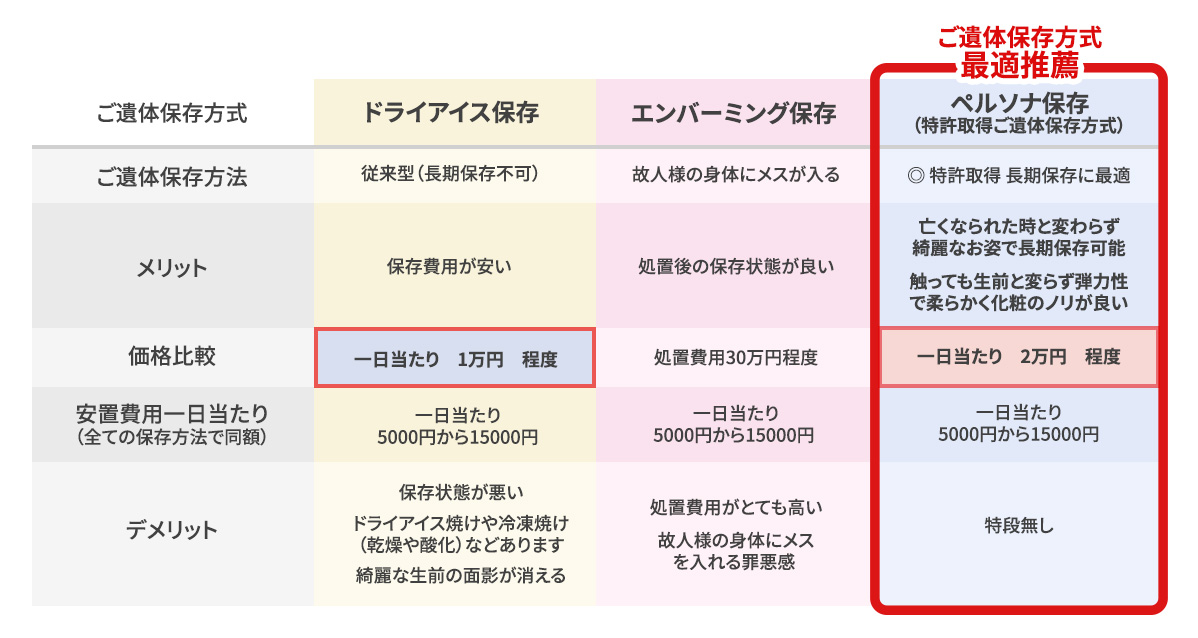ドライアイス不足と価格高騰が葬祭業を直撃
ドライアイス不足になった原因
ドライアイスの需要の増加
ネットショップや宅配の利用増加
コロナ禍で巣ごもり必要が生じ、ネットショップでの買い物や宅配を利用する人が増えたことで、冷凍食品の配送などでのドライアイスの使用量が増えました。 特に、生鮮食品やスイーツ、アイスクリームなどの温度管理が重要な商品の通販が拡大し、冷凍・冷蔵輸送の需要が急増しました。コロナ禍が終息したあとも、外出せずに欲しいものがすぐに配達してもらえる便利さから需要は増加。 その結果、ドライアイスの使用量が増加し、一部の時期には供給が逼迫するケースも見られます。

気温上昇の影響
近年、夏の気温が上昇しており、外気温が35〜40℃近くに達する日が増えてきています。そのため、これまでの方法では適切な温度を維持することが正しいとなり、ドライアイスの使用量を従来よりも増やしている状況となっております。特に、輸送や保管の際には、外気温の影響を受けやすく、従来と同じ量のドライアイスでは十分な冷却効果が得られないため、量を増やざるを得ない状況にあります。

ドライアイスの生産量の減少
ドライアイスの生産量の減少
製油所の老朽化
ドライアイスの原料となる二酸化炭素(CO₂)は、製油所の工業プロセスで発生する作る際に副産物として回収されます。回収された二酸化炭素は高圧で圧縮・冷却され、液体二酸化炭素となり減圧後の一部固体がドライアイスとなるため、大量の二酸化炭素(CO₂)が必要となります。
しかし、日本国内では製油所の老朽化による閉鎖が進んでおり、これがドライアイスの原料となる二酸化炭素の生産量減少に大きく影響を与えています。

供給の不安定化
国内のドライアイス供給が逼迫している中、生産設備のトラブルや定期メンテナンスによって工場の稼働が一時的に停止すると、全体として余裕がないため、供給量への影響が大きくなっています。
また、不足分を補うために韓国産のドライアイスをはじめとする輸入に頼っていますが、現代、中国や東南アジアでも需要が増加しており、十分な量を確保することが難しくなっております。
さらに、輸送コストの上昇や国際的な物流の混乱も、国内へのドライアイスの安定供給を憂慮しています。